伊香保挽歌
作詞・作曲 橘あきら
まぶた閉じれば 哀愁の街
尽きぬ思いを 心残して生きた
今日は湯の香に漂う 一人の旅路
来ました湯の町 夢の中まで
思い出すのは 霧の階段
伊香保の町
あなたと歩いて 夢追った町
忘れられない すずかけ小道あかり
祭りばやしの太鼓に 声はずませた
揃いの浴衣も あなたと二人
夜のツツジも 赤く燃えます
伊香保の町
別れ間際の 思い出榛名
ほほにひとひら とけた雪物語
なぜに消えゆく白い花 運命の命
凍てつく湯けむり 未練つないだ
忘れられない 今日も来ました
伊香保の町
随筆 伊香保挽歌
作・橘あきら
独り、わずかな月あかりのなかで手を合わせて言葉を紡(つむ)いでいます。合わせた掌(てのひら)は、月あかりと同じような透明感に包まれています。
遠くに宿の灯りが見えます。あるともない微(かす)かな風で芒(すすき)の穂が揺れています。
この風は、遠い遠いわたしたちふたりの過去から渡ってきた悠久(ゆうきゅう)の風でしょうか。
時は過ぎても、心のなかは昔のままのような気がします。不思議な不思議な気持ちです。
閉じたまぶたのなかで、今、わたしはあなたさまと語ります。帰りたくても帰れなかった故郷で、わたしはあなたさまと語ります。
これからお話しすることは、あの頃の、わたしとあなたさま、ふたりの短い短い物語です。とは言ってみたものの、さて、何から話したものでしょうか。
そうですね。――まずは、ふたりの馴れ初め(なれそめ)からお話ししましょうか。
あなたさまと知り合ったのは、この国が敗けた戦争の傷跡もようやく癒(い)えた頃のこと。
――ふたりが数え十五の歳の秋でした。
会うたびの何気ないあなたさまの優しい言葉に、いつしか、淡い淡い恋心を抱いたのが十七歳の夏でした。
今、手をつなぎ石段を歩いた時のあなたさまの手の温もりを感じます。「幸せになれますように」――短冊に幸せ願った七夕さまの夜、見上げた空に天の川。ツツジ咲く道を揃いの浴衣で歩きました。思いがけず、湯けむりのなかであなたさまに肩を抱かれました。そうそう、富岡製糸場の帰り道、水沢の観音さまに手を合わせ、ふたりで食べたお饂飩(うどん)の味が忘れられません。
帰らない昔が走馬灯(そうまとう)のように思い出されます。
ともに白髪の生えるまで、末を誓ったふたりにとって、毎日毎日が狂おしいほどに楽しい時期でした。親の許しもそこそこに、かわいい“宝物”も授かりました。
でも、運命といわれればそれまでですが、そんな幸せな日も長くは続きませんでした。思いもよらない凶事(まがいごと)が、あなたさまとわたしの仲を引き裂いだのです。
なぜ、なぜ?…目の前が真っ暗になりました。
小説伊香保挽歌
作・橘あきら
第1話
晩秋の榛名山は60年前と同じ燃えるような赤色に染まっていた。
温泉街に続く石段を上るゆきの眼に映る伊香保の町は、旅館やホテルも随分と増え、すっかり垢抜けた感じにはなっていたものの、先の戦争で空襲を受けなかったせいで、昭和20年代の温泉街の風情を残していた。
ゆきが尋常高等小学校を修了後に奉公した土産物屋の看板を見上げていた時、背後からふいに肩を叩かれた。
「誰かしら?」
後ろを振り返ったが、誰もいない。
首を傾げるゆきの耳に、チンチンチン――今度は渋川駅と伊香保温泉駅を繋いでいた路面電車の警笛が聞こえて来た。
「懐かしい音だこと。でも変ね。あの電車は、昭和30年代の初めに廃線になったし、私だって電車とバスを乗り継いで来たというのに、きっと空耳よね。今日の私はどうかしてるわ」
行き交う人は、独りごとを言いながら歩く老婆を怪訝な顔で見るが、ゆきにとっては、何故か、そんな視線さえ心地よく感じられる

不思議な気持ちだった。ゆきが、「大谷旅館」と書かれた暖簾が見える所にさしかかった時、に空が暗くなり、遠くで季節外れの雷の音が鳴った。「この時期に雷だなんて珍しいわね」――そう思ったのも束の間、目の前がまばゆいほどに明るくなり、その光の中で誰かが満面の笑顔で手を振っているのが見えた。
顔の部分はぼんやりしてはっきりしないが、あの笑い方、手の振り方は、ひょっとして?
「賢ちゃん?賢ちゃんでしょ。ゆきよ。会いに来てくれたの?」
熱い契りを交わし、二世を誓った忘れたくても忘れられない愛しい人である。
ゆきは、叫んだ。我を忘れて叫んだ。人目も憚らず叫んだ。
しかし、光の中の賢一は黙って微笑むだけである。
「会いたかった。会いたかった」――ゆきは、流れる涙を拭こうともせず、思いっきり手を伸ばした。
しかし、その手は空を掴んでいた。
それでもゆきは思った、否、信じたかった。
「届いた。賢一さんの手に届いた!」と。
第2話
ゆきの手に賢一のぬくもりが伝わって来た。昔と変わらない懐かしいぬくもりである。
「もう離さない」
ゆきは賢一の手を固く握りしめた。
「ゆき」
光の中から賢一の声が聞こえて来た。
「うれしい。やっぱり賢ちゃんは、わたしを迎えに来てくれたのね」
ゆきは、昔の仕草そのままに首を傾げて微笑む賢一を見上げながら言った。
「賢ちゃん、覚えてる?この道は、ふたりが初めて手をつないで歩いた道よ。そう、夏祭りの夜にお揃いの浴衣を着て…」
ふたりは、汗ばむほどにしっかりと手をつないで、すずかけの小径を歩いた。
大谷旅館の前を通り過ぎようとした時、賢一が足を止めた。
「玄関も屋根も、ふたりのために建て替えてくれた当時の雰囲気とちっとも変わってないわね。あっ、あの壁の色、確か賢ちゃんが是非に!って特別に注文した色だよね」
賢一が目を細めてうなづいた。

「『ゆきの女将姿はきれいだなあ』って言ってくれてる賢ちゃんが、今も時々、夢に出て来るのよ」
すっかり19歳の昔に戻ったゆきは、なおも賢一に話しかけた。
「建て替え中の少しの間、わたしがお勤めしていた片倉工業富岡製糸所(現・富岡製糸場)も今じゃ、世界遺産に指定されて随分と賑やかだけど、そうそう、賢ちゃんたら『急に会いたくなった』からって、製糸所まで、こっそりお弁当を持ってきてくれたわね」
賢一は、照れくさそうにゆきを見つめている。
「そういえば、伊香保神社にお参りした時、賢ちゃんが、『親子は一世、ぼくたちは二世まで』って書いた短冊をふたりだけの秘密の場所に隠したけど、あれはどうなったかしら?」
それまで微笑んでいた賢一の顔が一瞬、悲しそうな表情に変わった。
「ごめん、ごめん。決して賢ちゃんのことを責めてるわけじゃないのよ。今日は賢ちゃんに会えたことで、ゆきは幸せなんだからもっと話をさせてちょうだい」
一陣の風がすずかけの梢を、枝を揺らした。
「実は、あの後病院に…」
第3話
次の言葉が出ないゆきの肩を賢一が優しく抱き寄せた。
意を決したゆきが言の葉を継いだ。
「祝言まで1ヶ月。結核療養所からの退院を間近に控えたあの日、賢ちゃんが亡くなったという突然の電報が届いて…。目の前は真っ暗。気を失なって担ぎ込まれた病院で診てもらったところ…」
流れる涙を拭おうともせず、ゆきは一気に続けた。
「お医者さんが『奥さん、おめでたですよ』って。嬉しいやら、悲しいやら複雑な気持ちだったけど、この子は賢ちゃんの“生まれ変わり”だって思えて…」
大きく見開いた賢一の目から涙が溢れている。
「産みたい、どんなことがあっても産みたい。この子を立派に育てることが、私に課せられた使命だと思って、絶対に産もうと決心したの…」
大粒の涙で賢一の顔はくしゃくしゃである。
 「でもね。狭い街だし、今になって思えば無理もないけど、両親をはじめ、周りの人はみんな、女手ひとつで育てるのは無理だからって頭から猛反対。私も賢ちゃんの後を追おうと何度、榛名湖の畔に何度立ったことか…」
「でもね。狭い街だし、今になって思えば無理もないけど、両親をはじめ、周りの人はみんな、女手ひとつで育てるのは無理だからって頭から猛反対。私も賢ちゃんの後を追おうと何度、榛名湖の畔に何度立ったことか…」
話の先を急がせるかのようにゆきの肩を抱く賢一の手に力が入った。
「けど、負けなかったわ。賢ちゃんの“妻”として、絶対にこの子の母親になるんだって気持ちを奮い立たせて産まれたのが、賢ちゃんにそっくりの男の子。名前は明るい子に育つようにって『明』って付けたの」
ホッとしたかのように、賢一の表情が緩んだ。
「大谷旅館は弟の信ちゃんが継ぐことになって、女将になる夢は消えたけど、これからは賢ちゃんが遺してくれた、明と一緒に生きて行こと心に決めた矢先に、今度は私もまた肺結核で倒れてしまって…」
悲しげな賢一の表情を振り払うかのように、ゆきが言葉を続けた。
「広島から病院にお見舞いに来てくれた母の姉、そう賢ちゃんも会ったことがある村上の叔母様から、是非明を養子に欲しいって言われたの。もちろん私は断ったわ。でも、明の幸せを考えたらと思うと。迷いに迷った挙句、身を引き裂かれる思いで…」
第4話
「賢ちゃん、ごめんね。本当にごめんなさい」
溢れる涙を必死にこらえながら、ゆきは賢一の胸に顔をうずめた。
ゆきを抱きしめる賢一の目にも大粒の涙が浮かんでいる。
「明の幸せを思えばこそとはいえ、賢ちゃんが遺してくれた明を手放してしまったゆきを……許してください」
 泣きじゃくる我が子をあやすように賢一が、ゆきの背中をやさしく撫でる。
泣きじゃくる我が子をあやすように賢一が、ゆきの背中をやさしく撫でる。
涙、涙。溜まっていた胸のつかえを一気に吐き出すように、ゆきは明との別れを語り始めた。
「迎えに来た福山の姉さんに抱かれた明ったら、これからの身の上を知っているかのように精一杯の愛嬌を振りまいて…」
「見送りに行った渋川の駅のホームでは上りの電車が来るまで、紅葉のような手で私の指をギュっと握って…」
遠く過ぎ去った昔を昨日のことのように口にするゆき、そんなゆきの話を目を閉じて聞く賢一。――夕闇の中で立ちつくすふたりを深い霧が包み始めた。
・・・・・・・・・・・・
明の“新しい母”となった、ゆきの実姉・村上広枝が住む福山市は、古くは万葉の世から「潮待ちの港」として栄えた広島県第二の都市である。
その福山市にあって、広枝が嫁いだ村上家は、南北朝の時代から江戸末期まで芸予諸島を拠点に瀬戸内海で勇名を馳せた村上水軍の末裔で、当地でも屈指の網元として知られていた。
いわば、“お分限者”の後継ぎとして村上家に迎えられた明は、広枝たちの我が子に対する以上に深い愛情の甲斐あって、たいした病気も怪我もせず、ゆきの願い通りの明るい“福山っ子”として育った。
そんな明も今年で中学3年生、来年は高校受験である。
「明はどこの学校を受けるン?」
針仕事の手を休めた広枝が問いかけた。
「父さんと母さんに親孝行せにゃいけんけえ、市内の高校ならどこでもええじゃにゃあ」
「大事なことなんだから父さんにも相談せにゃいけんよ」
第5話
明は村上家のひとり息子として広枝夫婦の深い愛情のもと何不自由なく育てられた。
少々ヤンチャだが、気は優しいうえに、裏表のない性格は、小学校時代からクラスの人気者で、中学校では2年生から生徒会長を務めたほどである。
しかも、取り立ててガリ勉でもないのに成績は上位とあっては、誰しもが広島大学の附属高校か、県立の進学校を受験、その後は東京か大阪の大学に進むものと思っていた。
 しかし、明は“生まれ故郷”の福山を離れる気は露ほどもなかった。
しかし、明は“生まれ故郷”の福山を離れる気は露ほどもなかった。
「福山は瀬戸内の町、古き町、住む人 皆やさしき美しき町」――広枝の腕のなかで、物心つかぬうちから、愛読する『田舎教師』(田山花袋著)の一節をもじった詩を子守唄代わりに聞いてきた明にとって、福山こそが最高の町であり、人生を送る町と心に決めていた。
暮れも押し迫ったある日、広枝の頼みで鞆の浦に住む叔父宅に搗きたての鏡餅を届けた帰り道、自転車を止めて、夕闇に霞む弁天島、仙水島をぼんやりと眺めていた明の肩をふいに叩く者があった。
「明、こんなところで何をしょうるんにゃ~!」
「あっ、住職!」
八百年代初めに弘法大師によって開かれたとされる名刹・明正院の住職のいつもの穏やかな顔があった。
福山の名士でもある村上家とは代々の付き合いで、明も住職には小さい時から可愛がられてきた。
「夕暮れ時の仙水島も格別じゃ思うて、見ようたんよ」
「もうすぐ高校受験じゃろう。明はどこの学校を受けるんか?」
「まだはっきりとは決めとらんけど、合格できるところなら、どこでもエエと思うとるんよ(笑)」
「欲がないのう、明は。成績も良かろうに、附属でも受けりゃあエエのに。親父さんも明には大学まで行ってもらいたいと言うとるぞ。これからの時代は大学ぐらい出とらんとツブシも効かんと思うけえのう」
「勉強はそんなに好きじゃないし、自分自身、これからの人生で何を目標にしたらエエのか、正直なところ、分からんのよ」
第6話
年が明け、高校受験まで一ヶ月あまり。同級生たちは、それぞれの志望校を目指して眼の色を変えて直前の猛勉強に励んでいた。
しかし、明だけはまるで合格するのは当然とばかりに余裕綽々(よゆうしゃくしゃく)。学校から帰れば、毎日のように明正院の住職の許へ通って話し込んだり、鞆の浦の岸壁で釣り糸を垂れたり、およそ受験生らしからぬのんびりした日々を送っていた
明を村上家の跡取り息子として、掌中の珠の如く大事に育ててきた広枝にすれば、「あの子の成績なら合格は間違いなし」と思ってはいても、さすがに受験直前の明の態度には気が気でなく、顔を見る度に「試験は大丈夫なの?」と遠慮がちに聞くのだが、「心配せんでも、母ちゃんの子どもじゃけえ、バッチリよ~」と、屈託のない返事が返って来るのが常であった。
広枝は、こうした大事の前に殊更、無頓着を装う明の性格は母親に余計な心配をかけまいとする優しさの表れと思う反面、幼い頃から周囲の人間に対して人一倍細やかな心遣いを見せて大人たちを驚かせたゆきの性格に重ね合わせていた。
 明が受験したF高校は、県東部でも屈指の難関校だったが、担任の教師も驚くほどの優秀な成績で合格。
明が受験したF高校は、県東部でも屈指の難関校だったが、担任の教師も驚くほどの優秀な成績で合格。
入学式では、新入生を代表して挨拶する大役まで任された。
「それにしても、明は大したもんじゃ!ガリ勉でもないのにF高校にすんなり合格するなんて、さすがは村上の親父さんの血を引いとるだけのことはあるわあ~。もうすぐ受験じゃいうのに毎日、寺に来おって、村上水軍がどうした、毛利元就がこうしたなどと何時間も粘って、正直なところハラハラのし放しじゃったわ~(笑)」
合格の知らせに急いで村上家に駆けつけてきた明正院の住職の軽口にも「すべては仏様のお導きで~す」と冗談まじりの答を返す明だったが、広枝の前に正座して「母ちゃん、ありがとう」と頭を下げる明の姿を見た途端、広枝の胸に十五年前に伊香保で別れたきり
になっているゆきの笑顔がふと浮かんだ。
「ゆき、明は、こんなに立派に育ちましたよ」
広枝は心の中で静かに手を合わせた。
第7話
満開だった福山城の桜も一面の葉桜になった。
すっかり高校生らしくなった明の毎日は、中学時代とはうって変わった“優等生”に変身。判で押したように8時に家を出て、授業が終るや真っ直ぐに帰宅。夕食後は毎晩11時まで机の前に座る真面目なものであった。
あまりの変わりように心配した広枝が、「どうしたんよ~」と聞いても、明は「学生の本分は学問じゃけえのう」と笑顔で答えるのみで真意は分からない。
かと言って、友達付き合いをまったくしないガリ勉タイプではなく、持ち前の天真爛漫さで、他クラスの生徒のみならず、上級生にもものおじすることなく溶け込んでいく積極さは、良くも悪くも大人しい生徒が多いF高校にあって異色の存在であった。
檀家回りの途中に立ち寄った明正院の住職までもが「エライ頑張っとるようじゃのう。1学期の中間テストは学年で2番、夏休み前の後期試験はトップ。この調子なら広大どころか、東大も夢じゃないのう」と話題にしたほどで、明の名は福山中に知れ渡っていた。
 明日から夏休みという或る日、明が珍しく神妙な顔で広枝に話しかけてきた。
明日から夏休みという或る日、明が珍しく神妙な顔で広枝に話しかけてきた。
「母ちゃん、頼みがあるんじゃけど…」
「何ねえ?そんな改まった顔をして」
「あのなあ、買うて欲しいものがあるんよ~」
モジモジして次の言葉が出ない明に、業を煮やした広枝が問いかけた。
「はっきり言いなさい」
「オートバイ。バイクが欲しいんじゃけど…」
「オートバイだって?危ないからダメよ。第一、明は免許を持ってないでしょ」
「持っとるんよ。母ちゃんには内緒だったけど、昨日免許、貰うたもん」
「船の免許のことは聞いとったけど、バイクのことは初めて聞いたよ」
「船の免許は要らん!」
「いずれにしても母さんは反対、絶対に反対です!」
「じゃ、ええわ!自分で働いて買うけえ。もう母さんには頼まん!」
母と子の間に気まずい空気が流れた。
引き取って十五年。惜しみない愛情を注いできた明の初めての反抗であった。
第8話
「母ちゃん、行ってくるけぇ」
学校が休みの日には昼頃まで寝床でぐずぐずしている明が、今朝は朝食も摂らずに、明るい声で家を飛び出して行った。
台所に立っていた広枝は思わず時計を見て、「明、今日から夏休みでしょ。まだ7時前なのに、どこへ行くん?」
慌てて玄関に出たが、既に明の姿はなかった。
3日程前にオートバイを買って欲しいという明の願いをはねつけていただけに何となく気にはなったものの「鞆の浦に友達と釣りにでも行ったのかしら」と自分を納得させた。
しかし、昼ごはんの時間になっても、明は帰って来ず、心配になった広枝は、明正院の住職をはじめ、親しい友達の家など心当たりを探したものの、どこにも立ち寄った形跡はなく、不安は募るばかりだった。
「母ちゃん、ただいま~。ああ、腹減ったわ~。ご飯ある~?」
 6時を回った頃、ようやく明が帰って来た。
6時を回った頃、ようやく明が帰って来た。
「何処行っとったん?そんなに汗かいて。それにシャツもズボンも泥だらけじゃ」
「ご飯食べたら、すぐに出掛けるけぇ」
安堵した広枝の問いには答えず、慌ただしく自分の部屋に駆け込む明の背中に
「今からどこへ行くん?」
と声を掛けるが、「時間がないけぇ、ご飯、ご飯」と取りつく島もない。
洗ったばかりのワイシャツに着替えた明は、食卓につくや否や、まるで欠食児童のようにご飯をかき込んでいる。
「お昼ごはんは食べなかったん?」
「ふーっ、やっと生き返ったわ~。もう行かないけんいけん。今夜は遅くなるけぇ、カギは開けといてよ」
「どこへ行くんね。ちょっと待ちなさい、明」
唖然とする広枝が、声を掛けた時には、明は既に玄関を出るところだった。
「明、どこへ行くの?」
「母ちゃんには明日、ゆっくり話しするけぇ」
広枝の声を振り切り、懸命に自転車を漕いで着いたのは、市内隋一の歓楽街・御船町でも最大のキャバレー『銀世界』の前だった。
「よし、頑張らにゃ~!」
第9話
「あんなに慌てて明はどこへ行ったんじゃろう?」
広枝が気を揉んでいる丁度その頃、明は黒ズボン、白ワイシャツに蝶ネクタイの出で立ちでボーイとしての初日を迎えていた。
「ボーイさん募集。アルバイト可。<キャバレー銀世界>」――オートバイを買いたい一心で、学校の帰りに目にした貼り紙を頼りに張り切って飛び込んだものの、これまで“網元の跡継ぎ”として何の不自由もなく育てられてきた明にとってはそこで見るもの、聞くことのすべてが驚きの連続であった。
当時の『銀世界』は山陽道でも一、二を争う広さを擁する大型キャバレーで客席は300以上。生バンドの演奏で、人気歌手の松山恵子や五木ひろし、八代亜紀、冠二郎、矢吹健などがステージを飾っていた。
「福山にこんな世界があったんだ!」――目を輝かせる明だったが、当然のことながら新米のボーイに歌を聞いている暇はない。
 要領が分からないうちはトレンチにビールを乗せて運ぶのもおぼつかなく、何度も転びそうになったり、階段につまずいてアイスペールを落としたりと、悪戦苦闘の連続であった。
要領が分からないうちはトレンチにビールを乗せて運ぶのもおぼつかなく、何度も転びそうになったり、階段につまずいてアイスペールを落としたりと、悪戦苦闘の連続であった。
特に客席が満杯になる8時過ぎには、広いホールをまるでコマ鼠のように走り回らなければならず、体力には自信のあった明も、さすがに終業時間の12時になる頃にはクタクタ。足が棒のようになるほどであった。
しかし、何事にも負けず嫌いの明は、「ここで音を上げたら男じゃない。ワシは“銀世界一のボーイ”になるんじゃ~」と、自分自身を鼓舞。常にきびきびとホールを駆け巡る明の仕事ぶりは、支配人も感心する精勤ぶりであった。
一方、広枝にしてみれば明から「夏休みじゃけぇ、アルバイトしとるんよ」と知らされただけで、未だに何処で、どんなアルバイトをしているのか、肝腎なことも分からず、しかも帰宅するのは毎日午前1時前という尋常でない時間とあっては気が気でない。
意を決して問い詰めても
「母ちゃんの子じゃけぇ、心配せんでエエんよ」と生返事が返ってくるだけで心配は募るばかりであった。
第10話
あと数日でアルバイトも終るという或る日、終業後のホールの掃除に汗を流している明に、マネージャーから声が掛かった。
「ご苦労さん。よう頑張ったねえ。明君の仕事ぶりには、女の子の評判も上々だし、良かったら冬休みもウチでアルバイトしてくれんかな?」
仕事の要領もすっかり覚え、今や先輩ボーイからも一目置かれる存在になっていた明にとって、マネージャーの誘いは願ってもないこと。考える間もなく「よろしくお願いします」と頭を下げていた。
仕事ぶりを認められたという嬉しさもさることながら、連夜のショータイムに登場する、普段はテレビでしか観られない錚々たる歌手たちのステージ姿に、いつしか心魅かれるものを感じていたからである。
この時に抱いた歌手に対する秘かな憧れが、その後の明の人生を大きく変えることになろうとは、明自身ですら想像できなかったこと。まさに人生の“妙”と言うほかない。
 それはさておき、オートバイ欲しさに始めたアルバイトのはずだったが、皆勤賞の5000円を加えた16万5000円のアルバイト代を手にした時には、もはやオートバイに対する興味は、なぜか半減。今まで持ったことのない大金の使い途に思案した結果、出した答は広枝に対するプレゼントであった。
それはさておき、オートバイ欲しさに始めたアルバイトのはずだったが、皆勤賞の5000円を加えた16万5000円のアルバイト代を手にした時には、もはやオートバイに対する興味は、なぜか半減。今まで持ったことのない大金の使い途に思案した結果、出した答は広枝に対するプレゼントであった。
「母ちゃん、これで着物でも買えよ」
「気持ちは嬉しいけど、明が『銀世界』で一生懸命働いた汗の結晶なんじゃろ。オートバイを買うのは反対だけど、大切に貯金しときなさい」
「じゃけど、どうして『銀世界』でバイトしとったん
を知っとるん?」
「母さんは千里眼よ。大事な息子のことは何でもお見通し。そうでなきゃ、無鉄砲な明の母親は務まらんよ(笑)」
「母さんには参ったなあ」 久し振りの母と息子の和やかな会話であったが、1ヶ月前には見られなかった大人びた表情で頭を掻く明の横顔に広枝は、ふと「この子は、私の手の届かないところへ行ってしまうのではないか」と胸騒ぎを覚えた。
第11話
『銀世界』での明のアルバイトは、夏休みはもちろん冬休みも春休みも皆勤賞という精勤ぶりで高校を卒業する直前まで続いた。
マネージャーも明の熱心さに押され、年齢詐称を承知で採用したものの、どうせすぐに音を上げるだろうと高を括っていたのだが、予想に反する明の頑張りに驚嘆。2年生の冬休みにはボーイ長に抜擢したほどで今や、明は入舟町界隈では“未成年ボーイ長”として知らぬ者はいない人気者となっていた。
だからといって、勉強がおろそかになったわけではなく、成績は常に学年でもトップクラスを。優秀な成績に免じて校則で禁止されている夜間のアルバイトを見て見ぬフリをしていたクラスの担任教師でさえ「ちっとは明を見習え」と引き合いに出す有様であった。
そんな明の“勇名”が、広島県第2の都市とはいえあらゆる面に、濃密な人間関係が色濃く残る福山にあっては、時を経ずして、人々の口端に上るのは当然のこと。無論、明の噂は広枝の耳にもしっかりと届いていた。
 「明は、網元の若い時と違うて、まさしく文武両道のお手本。村上の跡取りではもったいないのう(笑)」
「明は、網元の若い時と違うて、まさしく文武両道のお手本。村上の跡取りではもったいないのう(笑)」
冗談だとは分かっていても、夫とは正反対の明の性格を話題にされる度に、広枝は不安な気持ちが胸に拡がるのを覚えずにはいられなかった。
そんな或る日のこと。般若湯を聞こし召しているのか、玄関先で明正院の住職が、いつにない大声で明を呼でいる。
「法事の帰りに寄ったんじゃが、明は居るか?土産を持って来たぞ」
「あらあら、ご住職。今日は随分とご機嫌で。明は、まだ学校ですよ」
「今や明は街中の人気者じゃ。行く先々で『たいしたもんじゃあ~!』ちゅう話で持ち切りや。もし、伊香保のゆきさんが明の評判を聞いたら、きっと『産んで良かった。姉さんに預けて良かった』って思うじゃろうなあ~!」
折しも、学校から帰った明は、四脚門をくぐり、格子戸に手を掛けようとした時に聞こえてきた、住職の大きな声に足を止めた。
「ゆきさん?伊香保のゆきさんって誰なんだろう?」
第12話
「は~い、ビールと浦賀沖で獲れた鯵のお刺身よ~」
丁度その頃、明の産みの母・ゆきは京浜急行横須賀中央駅前に近い食堂『みうら屋』で疲れた身体に鞭打ちながら、テンテコ舞いの毎日を送っていた。
祝言直前に賢一と死別、ふたりの“愛の証し”である明は、遠く離れた瀬戸内の町へ。――夢破れたゆきにとって、伊香保は居心地の良い場所ではなかった。
それでも、ゆきにとって伊香保は賢一との思い出の地。虚ろな気持ちで、物思いにふける日々を送っていた。
「ゆき姉さん、そんなに思い詰めてると体を壊すよ。良かったら、遠縁の人間が横須賀で食堂をやってるんだけど、気晴らしも兼ねて行ってみませんか?」
げっそりと痩せたゆきを見るに見かねた賢一の弟の勧めで、思い切って横須賀に来たゆきだったが、朝鮮戦争の余熱が残る当時の横須賀は、伊香保とは打って変わった賑やかさ。迷彩服姿の米軍兵士が行き交う街は、ゆきにとっては、目にするものすべてが初めての別世界であった。

『みうら屋』は、表の看板には、ただ食堂と書かれていたが、ワンフロアに洋食をはじめ、和食、寿司、中華などのコーナーを擁する和洋折衷のハイカラさで人気を集めていた。
目抜き通りに面していることもあって客はひっきりなしで、開店から閉店まで大繁盛、特に夕方からは行列ができるほどであった。
傷心のゆきにとっては、ぼんやりする暇もない毎日の忙しさは、かえって好都合で、伊香保を発つ前の沈んだ表情も徐々に消え、持ち前の器量よしもあって、常連客からは『みうら屋』の看板娘と呼ばれるほどの評判であった。
横須賀での勤めにも慣れた2年後、ゆきは『みうら屋』の板前だった久志と所帯を持ち、4畳半ひと間ながらも、ようやく落ち着いた生活を送れるようになったのも束の間、些細なことで久志が客と喧嘩したことでクビ。ならばとギター片手に「流し稼業」に転じたものの、安定した稼ぎには程遠く、そのうえお定まりの酒とギャンブルに熱中。
ゆきの両肩にのしかかる苦労は、新婚生活と呼べない荒んだものであった。
第13話
飲む・打つ・買う――三拍子揃った久志の放蕩は改まるどころか、日を追ってエスカレート。初めの頃はゆきの小言に二日酔いの頭を畳にこすりつけて謝っていた久志だったが、そんな殊勝な態度もその場限り。
「好きで一緒になった仲。そのうち目を覚ましてくれるに違いない」というゆきの願いも虚しく、今では滅多に家に帰ることもない、夫婦とは名ばかりの毎日であった。
それでもゆきは、そんな辛さをおくびにも出すことなく気丈に振る舞い、『みうら屋』での目の回るような忙しさにかまけて気を紛らわせていた。
そんな或る日、いつものように開店の準備に追われていたゆきの許に、2年近くも家に寄りつかなかった久志が市立病院に担ぎ込まれたという連絡が入った。
いくら放蕩の限りを尽くした夫でも、かりそめにも所帯を持った仲である。半狂乱になりながら病院に駆けつけたが、ベッドに横たわった久志は既に危篤状態。数時間後、一度も目を開けることなく、泣き叫ぶゆきに手を取られたまま帰らぬ人となった。

葬儀の終わった夜、ゆきは白木の箱を前に一晩中泣き明かした。
「何故、私ばかりがこんな目に遭うの?」――賢一に続いて久志までをも亡くしたゆきは、自分の運命を呪った。
しかし、打ち沈んでいてはますます気が滅入るばかり。初七日を終えた翌日から『みうら屋』に出たものの、注文を取り違えたり、何度も食器を落としたり、何事にもてきぱきとしていた、いつものゆきとは別人であった。
「このままでは迷惑をかけるばかりでは~」――四十九日の法要を終えた夜、ゆきは、『みうら屋』の主人の熱心な引きとめを振り切って15年間の思い出が残る横須賀の地を後にした。
さりとて、行くあても定かでなく、遠縁が住む練馬の大泉学園を目指したものの、連絡もせぬまま、いきなりの訪問ではと思案。駅前のベンチに座ってぼんやりとしていたゆきの目に映ったのが『俳優さん急募!寮完備』の貼紙だった。
「これだ!」――ゆきは、何かに導かれるように公衆電話に飛びついていた。
第14話
「う~ん。せっかく面接に来て貰ったんだけど、現在募集しているのは女子大生なんだけどねえ」
ゆきが尋ねた「さくら芸能プロダクション」は、映画やTVドラマなどにエキストラを斡旋する、今風にいえば、人材派遣会社であった。
「そこを何とかお願いします。多少はお芝居の経験もあります。どんな役でもいといません。どうか採用してください」
何としても採用してくれなければ、今夜の泊まる場所もないのである。なりふりなど構っていられない。遥か昔、十代の頃に伊香保の温泉祭りの素人芝居で、村娘役で演じたことを“経験”に加えて必死の形相ですがりついた。
「芝居の経験があるの?」
「はい。伊香保の温泉祭りで…」
準主役とはいえ、たかが素人芝居にすぎない。胸が張れる“芸歴”ではないどころか、ヘタをすれば経歴詐称になりかねないだけに、語尾は途切れてしまった。

てっきり鼻であしらわれると覚悟していたところ、返ってきたのは意外な言葉であった。
「あんた、伊香保の出身かね?俺は前橋の生まれだ。懐かしいなあ。よし、上州人のよしみで、特別に採用しよう。そうだな、明後日から田宮さんが主演の『白い巨塔』がクランクインするから、その現場に入って貰おうかな」
まさに地獄に仏である。
「良かった~」…胸を撫で下ろしたものの、エキストラとはいえ、大見栄切って飛び込んだ世界で、この先やっていけるのだろうか?考えれば考えるほど、じわじわと広がる不安に心が縮みっ放しだったが、他に行くあてもないゆきにとっては肚をくくるしかない。
意を決して撮影所に足を運んだ“初出勤”の日。助監督直々に指示された役柄は、なんと田宮二郎扮する財前五郎付きの看護婦長の役。――「セリフもふたつほどあるからよろしくね」いきなりの“大役”に、ゆきの頭は真っ白になって
しまった。
第15話
「お疲れさ~ん」――撮影を終えたゆきの明るい声が部屋中に響いた。
「あなた、今日が初めてなのにセリフもしっかりしてたし、やるじゃない。わたしなんか4年もやってるのにセリフをもらったのは2回だけよ」
同じ看護婦役で出ていたプロダクションの先輩女優をうらやましがらせた。
そう言われても、ゆき自身はピンと来なかった。
事実、ゆき自身、「よ~い、スタート!」の声が掛かるまではドキドキ、オドオド。「財前先生、院長がお呼びです」という短いセリフにもかかわらず、なかなか覚えられなかったのにいざ本番となった途端、自分でも驚くほどスラスラと口に出て来たのには不思議な気持ちであった。「案外、わたしに向いているのかも。明日も頑張らなくちゃ!」
度胸満点、ゆきの大部屋女優らしからぬ初日の演技に目をつけた助監督の計らいで、翌日の撮影では予定にはなかったセリフまで割り当てられ、主役の田宮二郎からも「ゆきさんは、筋がいいね」と声をかけられたほどであった。

「今までは銀幕でしか観たことがなかった大俳優に誉められた」――必死の思いで飛び込んだ芸能界。その芸能界の隅っことはいえ、仕事の楽しさを実感したゆきは、初めて安住の場所を見つけたような気がした。
それからのゆきは、頼まれた映画には、どんな役でもすべて出演した。
勝新太郎、市川雷蔵、東野英治郎、波島進――もちろん大部屋女優としてではあったが、当時の人気俳優たちとも“共演”。市川雷蔵などは、わざわざゆきを指名するほどであった。
何事にも一生懸命に取り組むゆきのひたむきさに、プロダクションの社長も割の良い役柄を回してくれるようになった。お蔭で多少の蓄えもでき精神的にも充実した日々を送っていた。
そんな或る日、仲の良かった大部屋仲間から、その後のゆきの運命を大きく変えることになる「一諸にお店をやってみない?」という話が持ち込まれた。
第16話
「新宿・歌舞伎町にクラブに丁度いい広さのお店があるのよ」
「新宿ですって?」――突然、しかも手回しの良い誘いに、ものおじしないゆきも、さすがに面食らった。
大部屋女優ながらも、飲みこみが早く、時代劇から現代劇まで臨機応変に役柄をこなすゆきには、監督をはじめ主演俳優からも起用依頼が殺到。「いつか、ちゃんとした役をもらえる女優になれるのでは?」と希望に胸を膨らませていただけに尚更である。
しかし、さくら芸能プロダクションに籍を置いて以来、まるで姉のように面倒を見てくれた先輩・圭子の誘いだけに、無下に断ることも出来ない。
その場は、「やりたい気持ちはあるけど、突然のお話だから1週間ほど考えさせて」と生返事を返したものの、相談する相手もいないゆきは思案に暮れた。
「困ったなあ。どうしようかしら?」「わたしなんかにお店なんて出来っこないし…」「だけど、お世話になった圭子姉さんの誘いだし…」

「でも、『みうら屋』の経験を生かせば、案外出来るかも…」「いや、ここは東京。横須賀とはわけが違うし…」いくら考えても堂々巡りである。
結論の出ないまま、圭子に返事をする日が来た。
「どう?決まった?」「やってみようかしら」
直前までは断る気持ちだったにもかかわらず、ゆきは、あまりにも圭子の明るい表情に釣られるように、ふたりでお店を出すことを“承諾”していた。
「ありがとうね、ゆきちゃん。絶対、成功するようににがんばろうね」「はい。圭子姉さんと一緒なら、わたしも一生懸命、やれるような気がします。すべて圭子姉さんにお任せしますので、よろしくお願いします」
お店の名前は『幸』。圭子がママで、ゆきはチーママ。圭子はお店に専念するが、当分の間、ゆきは女優業と掛け持ち。――ついさっきまで迷っていたのが嘘のように、話はあれよあれよという間にまとまった。
第17話
水商売の経験が一度もない大部屋女優ふたりの無鉄砲?としか言いようがない『幸』の開店だったが、オープン当日から来店者が入りきれないほどの大賑わいが続いた。
店の入口には、ゆきを殊のほか可愛がってくれた田宮二郎をはじめ、“共演”したことのある市川雷蔵、勝新太郎、京マチ子など今をときめく銀幕の大スターたちから贈られた開店祝いの花輪がズラリと並んだ。
その花輪をかき分けて、これまでにゆきや圭子を起用してくれた映画監督に連れられた助監督や照明・音声さん、果ては大道具・小道具さんたちが入れ替わり立ち代わり日参。『幸』の店内は、さながら“大泉映画村”の住人たちが、そっくり引越してきたのでは?と見間違える日が何日も続いた。
連日連夜の盛況が物見高い“歌舞伎町雀”の間で話題にならないはずがなく、噂が噂を呼び、その噂が客を呼ぶ。――まさに順風満帆。開店して3ヶ月も経たないうちに『幸』は、映画関係者のみならず各界のお歴々が足を運ぶ“高級クラブ”の地位を確固たるものにした。
 喧騒のひとときが過ぎたある夜。――ゆきと圭子は久しぶりに二人だけでカウンターで向き合った。
喧騒のひとときが過ぎたある夜。――ゆきと圭子は久しぶりに二人だけでカウンターで向き合った。
「最初はどうなることかと、不安いっぱいの開店だったけど、こんなにお客様が来てくれるなんて。みんなゆきちゃんのお蔭よ」
「いえいえ、圭子姉さんがママ一本で頑張ってくれているからですよ。私こそ姉さんには大感謝。これからも宜しくお願いします」
「こちらこそ宜しくね。さあ、今夜もいっぱいのお 客様で、ゆきちゃんも疲れたでしょう。映画と掛け持ちだし、明日は桜プロの社長が紹介してくれた手のモデルの撮影もあるでしょ。早く帰った方がいいわよ」
「大丈夫ですよ。私はまだまだ若いし(笑)これぐらいで“白魚の手”は“煮干しの手”にはなりませんから。圭子姉さんこそ毎日遅いんですからお先に帰ってください」
「ねえねえ、これから面白いお店にいってみない」
「面白いお店?わっ、行ってみたいな」
第18話
片付けもそこそこにゆきと圭子は店を出た。
開店以来、一日の休みも取らず、しかも昼間は撮影に手のモデルと、てんてこ舞いだっただけに体は鉛のように重かったが、思いがけない圭子の誘いに何故か、ゆきの心は弾んだ。
「でも、面白いお店ってどんなお店なの?」
ゆきは目を輝かせて聞いた。
「どうしたの、ゆきちゃん。そんなに浮き浮きしちゃって?」
「だって、圭子ねえさんとふたりでお出掛けするなんて初めてなんだもん」
圭子は、まるで少女のようにはしゃぐゆきの耳元で囁いた。
「真実の真に樹木の樹と書いて真樹(まき)。その子がいるお店に行くのよ」
「あらあら。圭子姉さんも隅に置けないわね。いつの間にそんなお店を見つけたのよ(笑)」
「この前、お客さんに連れて行ってもらったホストクラブなんだけど、百聞は一見に如かず。疲れなんか吹っ飛ぶぐらい、とっても面白いんだから…」
「圭子姉さんがお気に入りの真樹っていう子は、どんな感じの子?」
 「うん。ちょっと2枚目半なんだけど、底抜けに明るい子で、話もおしゃれだし、歌はプロの歌手顔負けの上手さなのよ。年甲斐もなく、わたし一遍にファンになっちゃった」
「うん。ちょっと2枚目半なんだけど、底抜けに明るい子で、話もおしゃれだし、歌はプロの歌手顔負けの上手さなのよ。年甲斐もなく、わたし一遍にファンになっちゃった」
「へ~っ。わたしも会ってみたいな、その真樹っていう子に」
「確か、生まれは広島の福山って言ってたけど、時々、出てくる広島弁がまたかわいいのよ(笑)」
「福山ならわたしも姉が嫁いでるし…」
その時、道路の向こう側から声が掛かった。
「ゆきちゃ~ん」
声の主は、昨日までゆきも出演していた映画の監督であった。
「これからお店に行くところだったんだけど、もう店仕舞いしちゃったの?次回作の件で、ちょっと話があるんだけど…」
監督直々のお声掛かりでは、残念だが、ホストクラブ行きは諦めるしかない。
「圭子姉さん、悪いけど今度また誘ってください」
第19話
「残念だけど、お仕事が一番。せっかく監督が声をかけて下さったんだもの、行ってらっしゃい。今夜はわたしひとりで顔を出してくるから。頑張ってね」
「は~い。行ってきま~す。圭子姉さんも飲み過ぎないようにね(笑)」
監督の許に小走りに駆けて行くゆきを見送った圭子は、気を取り直して『恋』(れん)のドアを押した。
「いらっしゃいませ。あれっ!圭子ママだけなんですか?」
出迎えた真樹は、圭子の背中越しに、一緒に来店すると聞いていたゆきの姿を探した。
「ごめんね。お店の前まで来てたんだけど、急に撮影の打ち合わせが入って来れなくなっちゃたのよ。近いうちに必ず連れてくるから…」
フロアの奥の席に着いた圭子の横で馴れた手つきでブランデーの水割りを作りながら真樹が聞いた。
「圭子ママ、ゆきさんってどんなひと?」
 「どんなって?――う~ん。あのシャンデリアみたいに色が白くて、わたしに似て美人だし(笑)可愛い妹みたいな存在かな。お店ではわたしの片腕、撮影所では大部屋のなかではピカイチの売れっ子さんよ」
「どんなって?――う~ん。あのシャンデリアみたいに色が白くて、わたしに似て美人だし(笑)可愛い妹みたいな存在かな。お店ではわたしの片腕、撮影所では大部屋のなかではピカイチの売れっ子さんよ」
「素敵な方なんですね。そこまで聞かされたらますます会いたくなりました。今度は是非、お連れして下さいね」
「わたしは信州の生まれだけど、ゆきちゃんはお隣りの上州。あの有名な伊香保温泉で産湯を使ったから色白なんだって、いつも聞かされてるのよ(笑)」
いかにも愛おしいという口ぶりで圭子はゆきの話を続けた。
「そうそう、お姉さんが真樹ちゃんと同じ福山に嫁いでいるみたい。お家は村上水軍の血を引く大きな網元で、すごいお金持ちだって言ってたわよ」
「え~っ!僕の実家も網元だけど、ゆきさんのお姉さんとは知り合いかも?」
あまりにも奇遇すぎる圭子の話に真樹の胸中を不思議な稲妻が走った。
「さあダンスタイムよ。真樹ちゃん、踊りましょ。『星降る街角』だからジルバよ」
第20話
圭子と真樹がジルバを踊っている頃、再び店に戻ったゆきは、カウンターで監督と向かい合っていた。
「もう少し、早くいらして下されば圭子ママもいたのに…」
屈託のない笑顔でビールを注ぐゆきに、監督がいつにない真面目な顔で口を開いた。
「実はね、ゆきちゃん。さっきまで制作局長と次回作の打ち合わせをしていたんだけど…」
ビールを一気に飲んだ監督が言葉を継いだ。
「急に、スケジュールの都合がつかなくなったヒロイン役の松風ひろみの代役を誰にしようか?ということで、話し合っていたんだが、作品のイメージにピッタリの女優が見つからなくて、思いきってゆきちゃんの名前を出したところ…」
「えっ、わたしが松風さんの代わりですって」
ゆきの驚きをよそに、監督は手酌で注いだビールを飲みながら話を続けた。
「局長も『いいじゃないか。大部屋でもあの子なら演技もしっかりしてるし、松風の代役も務まるんじゃないか』って、すんなり決まったというわけだ」
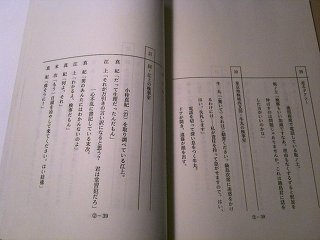
ゆきはまだ半信半疑だった。
大部屋女優のなかでは、それなりに評価されていたとはいえ、看板女優の松風ひろみに代わって主役に抜擢されるなんて、ありえないことだけに無理もない。
「クランクインは来週だからね。しっかり台本を読み込んでおくように。じゃあ、また明日!」
未だ夢見心地のゆきは、監督が帰ったのも気付かぬまま、手渡された台本を握って立ちつくしていた。
小さくてもいい、せめてポスターに自分の名前が載る日を目標にしていたのに、いきなり主役だなんて…!
頬をつねったり、手にした台本を何度も裏返しにしたり、また表にしたり。ようやく「夢じゃない」と、我に返ったゆきだったが、一旦こうと決めたら何事にも全力でぶつかっていくのが身上だけに気持ちの切り替えも早かった。
「きっと神様がゆきにくれたご褒美かも。頑張らなくちゃ」――ようやくゆきの顔に血の気が戻った。
第21話
冷静になったゆきは監督から渡された台本を改めて見直した。
表紙にはタイトルの『しまなみ物語』。そして出演者名が書かれた2ページ目の最初の行には、ヒロイン役のゆきの名前がある。
物語は、瀬戸内海に浮かぶ大三島の町立病院を舞台にした悲恋ドラマである。
大三島は、今治市(愛媛県)と三原市(広島県)の間に位置する芸予諸島の中心的な島で、大山祇神(おおやまつみがみ)が祀られていることで「神の島」と呼ばれ、戦国時代には村上水軍が水城を構えていたことで知られている。
ヒロインであるゆきの役どころは、島の病院に勤務する看護婦。大ヒットした『白い巨塔』での看護婦長役など、これまで何度も演じてきた、いわばゆきにとっては”当たり役”である。
とはいえ、大部屋女優からいきなりの主演。――また心臓がドキドキし始めた時である。
「ゆき、おめでとう!ゆきなら、大丈夫だよ」
どこからか、優しさに溢れた声が聞こえた。
「圭子姉さん?そんなわけないし…誰かしら?」
回りを見渡しても誰もいない。
 「聞き憶えのある声だったんだけど…。嬉しさのあまり、耳がおかしくなったのかも。それより監督の言いつけ通り、もっと台本を読み込んでおかなくちゃ」
「聞き憶えのある声だったんだけど…。嬉しさのあまり、耳がおかしくなったのかも。それより監督の言いつけ通り、もっと台本を読み込んでおかなくちゃ」
支度も取らぬまま、ゆきは再び台本を手に取った。
さっきまでの不安が、徐々に自信に変わっていくのを感じながら、ゆきは時間が経つのも忘れて何度も何度も読み返した。
『幸』の開店祝に田宮二郎から贈られた置時計が7時を指した時、カウンターの電話が鳴った。
「ゆきちゃんかい。おはよう。台本、読んだかい」
監督からだった。
「はい。読ませて戴きました」
「ゆきちゃんの抜擢を局長に直談判した二郎さんも『あの子なら大丈夫!』って太鼓判押してたからね。頑張ってよ。早速だけど今夜、大三島に出発するからね。準備しておくように」
「えっ!田宮さんが…」 ゆきの目から、また大粒の涙がこぼれ落ちた。
第22話
『しまなみ物語』の大三島での撮影期間は約3週間の予定だった。
大部屋俳優時代は長くても間隔を置いて1週間程度だっただけに、さすがに思い切りの良いゆきも、期待と不安が入り混じった胸が高鳴った。
圭子に撮影中の不在を知らせる電話を架けた後、ゆきは支度を整えた。
今までは衣装もすべて重いキャリーバッグを自分で運んでいたのだが、ヒロイン役となればすべてが他人任せであり、今日のゆきは小さなボストンバッグひとつである。
集合場所の東京駅には既に監督以下、撮影隊一行が揃っていた。
「今夜は衣装合わせのため大阪で泊まりだ。明日午後、三原で大道具さんと合流。フェリーで全員、大三島に渡るから、各自そのつもりで…」
監督の簡単な指示の後、撮影隊は新幹線に乗り込んだ。
ゆきにとって初めての新幹線、しかもグリーン車。まるで慰安旅行のようなウキウキ気分だったが、3時間後には大阪に到着。宿泊するホテルで全員の衣装合わせが終了したのは午前零時過ぎであった。
 部屋に戻り、何気なくテレビをつけたゆきの目に映ったのは福山・鞆の浦の観光案内番組だった。
部屋に戻り、何気なくテレビをつけたゆきの目に映ったのは福山・鞆の浦の観光案内番組だった。
「鞆の浦だ。広枝姉さんは元気かな? 明は大きくなったかな?」
ゆきは備え付けの時刻表のページをめくった。
「え~っと、三原駅は福山、新尾道の次なんだ。監督にお願いして、みんなより早目にホテルを出て福山に寄り道していいか、お願いしてみようかしら」
翌朝、ゆきは、はやる心を抑えて新大阪駅発の新幹線に乗った。
車窓を流れる風景は穏やかだったが、それもなかばうわの空。倉敷駅を過ぎた頃からゆきの心臓はドクンドクンと音を立てていた。
福山駅で降りたゆきは、小走りで鞆鉄バスターミナルの公衆電話まで走った。
「もしもし、もしもし、広枝姉さん。ゆきです」
「えっ、ゆきちゃん。ゆきちゃんなの!」
懐かしい姉の声が受話器から聞こえてきた。
第23話
「広枝姉さん…」
溢れ出る涙で後の言葉が続かない。
「どうしたの、ゆきちゃん?」
気丈な姉の声が受話器を通して耳に響く。
「今、どこなの?」
「福山駅前の公衆電話から架けています」
「あらっ、福山に来とるん?」
「これから映画の撮影で三原駅まで行って大三島に渡る予定なんですけど、途中下車して…」
「時間、あるんじゃろ。ウチに寄っていきゃあええが。積もる話はそれから。鞆鉄バスで鞆の浦行に乗って仙酔島前で降りりゃあええけえ。バス停まで迎えに行くけぇ~」
「は、はい」
否も応もない。――初めて聞くテンポの良い広島弁に圧倒されたゆきの足は停留所に向かっていた。
芦田川に沿った舗装道路を走ること30分。車窓から徐々に潮の香りが流れ込んできた。
「きれいな海だこと。小さな島がいっぱい!」
初めて見る瀬戸内の島々に見とれる間もなく車内放送が次が仙酔島であることを告げた。
 前方の停留所に手を振る広枝らしき姿と袈裟衣装の老人が見えた。
前方の停留所に手を振る広枝らしき姿と袈裟衣装の老人が見えた。
「広枝姉さ~ん!」
ゆきも窓から身を乗り出して負けじとばかりに手を振り返した。
バスが止まった。駆け寄る広枝。転げ落ちるようにバスから降りるゆき。伊香保で明を預けて以来、20年ぶりの再会である。
「ゆきちゃん!」
「広枝姉さん!」
ふたりは泣きながらひしと抱き合った。
「おう、ゆきさんか!」
「ゆきちゃん、こちらは明正院の住職さん。明が、小さい時分から随分と可愛がって貰うたんよ。丁度、ゆきちゃんから電話があった時にお見えになっとったけぇ一緒に…」
「初めまして。妹のゆきです。明が大変お世話になったそうでありがとうございます」
「さあさ、話したいことは山ほどあるし、ここでは何じゃけえ…」
眼前に霞む仙酔島の上空で2羽のカモメが啼いた。
第24話
ゆきを真ん中に三人は坂道を登った。
その道すがら、広枝は20年間の空白を一気に埋めるように矢継ぎ早にゆきに話しかけた。
「さっきの電話で映画の撮影で大三島に渡ると言うとったけど、ゆきちゃんは俳優さんなん?」
「ええ。でも、まだまだ駆け出しです」
「ゆきちゃんが映画俳優になっていたなんて、全然知らんかったけど、すごいじゃない!」
「そんなぁ。ワキ役ばかりで大したことは…」
「それで今度の映画は、どんな役なの?」
「『しまなみ物語』っていうタイトルなんだけど、初めての大きな役で看護婦役なんです」
「何時まで福山に居られるん?今夜は泊まっていくんでしょ」
「これから三原駅で監督さんたちと合流しなくちゃいけないので、あと2時間ぐらいしか…」
がっかりした表情の広枝の後を接いで、住職が言葉を続けた。
「器量もエエし、道理で垢抜けとると思うたけど、女優さんとはのう。東京の大学へ行った明も歌手になりたいいうて頑張っとるようだし、やっぱり血は争えんもんじゃのう」

「明が…東京に…?」
泣き泣きとはいえ、産まれて間もないわが子を手放した、いわば母親失格のゆきである。
明のことをいつ切り出そうかと、ジリジリしていたところに、思いがけず住職の口から明の名前が飛び出した。
「明…」
会いたくもあり、会うのが怖かった明が、わたしと同じ東京の空の下にいるなんて、思ってもいなかっただけにゆきの心は揺れた。
「なあ、広枝さん。ゆきさんの時間もないし、今日はウチの寺で、仙酔島の絶景を見ながら姉妹再会の宴というのはどうじゃろう」
涙ぐむゆきの心中を察した住職の計らいである。
ゆきと広枝は、仙酔島が目の前に見える明正院の本堂に腰を降ろした。
「わあ、きれいな島!」
「あの松の木に登っていた明が落ちたことがあって大変だったんよ~(笑)」
第25話
「あれは何年前じゃったかのう。木から落ちた山鳩のヒナを『母ちゃんとはぐれたら可哀想じゃけん巣に戻したるんよ』言うて登ったらしいんじゃが、反対に自分が落ちてしもうて。あの時は肝を冷やしたのう、広枝さん(笑)」
「母ちゃんとはぐれたら可哀想じゃけん…」――悪気がないのは分かっていても、住職の言葉がゆきの胸に突き刺さった。
「ごめんなさい、明」
ゆきは心の中で掌を合わせて何度も詫びた。できることなら声を出して泣いて詫びたかった。
しかし、そんなゆきの気持ちも構わず、広枝と住職がしきりに話しかける。
何しろ20年ぶりの実の姉妹の再会である。
積もる話で心が躍るのも無理からぬことだが、明のことで気もそぞろのゆきは適当に相槌は打つばかり。
住職が煎れてくれたお茶に口をつけることもないまま瞬く間に別れの時がやってきた。
「姉さん。明のこと、母親失格のわたしに代わって立派に育てていただいて、本当にありがとうございました。そのうえご住職にもお会いできたし、本当に福山に来て良かったと思います」
 「ゆきちゃん。水臭いこと言わないでよ。ふたりっきりの姉妹じゃない。お父さんも喜ぶと思うから今度はゆっくり来てね」
「ゆきちゃん。水臭いこと言わないでよ。ふたりっきりの姉妹じゃない。お父さんも喜ぶと思うから今度はゆっくり来てね」
「は、はい…。ありがとうございます。機会を作って、またお邪魔させていただきます」
こう作り笑顔で答えたものの、今さら「明に会える資格はわたしにはない」と固く決めていたゆきにとって、広枝の言葉は嬉しくもあり、また辛かった。
福山駅までは住職が車で送ってくれた。
窓から入る風は心地良かった。
ゆきは、徐々に遠ざかって行く仙酔島を目に焼き付けるように見続けた。
「あの角を曲がれば、駅はもうすぐじゃ」
その時、住職の言葉に合わせるように広枝が、そっとゆきの手に紙片を握らせた。
「ん?」
ゆきの顔を見つめて、広枝は優しくうなづいた。
第26話
住職の運転する車が福山駅に着いた。
「こだま号」に乗れば、三原駅までは20分と少しである。
「広枝姉さん、それにご住職、本当にありがとうございました。20年ぶりに姉さんに会えて嬉しうございました。今後とも明のことをよろしくお願い申し上げます」
改札口でゆきは深々と頭を下げた。
「この世に二人しかいない姉妹じゃない。他人行儀なことは言いっこなしよ」 泣き笑いの顔で広枝がゆきの肩を抱いた。
「姉さん、もう大丈夫だから、ここで…」
涙声のゆきの言葉をさえぎって広枝と住職は、ホームまで見送りに来た。
13時11分発の博多行「こだま741号」が1番線に静かにすべり込んできた。
列車は空いていた。
乗り込んだゆきは、窓際に席を取った。
広枝が顔を車窓にくっつけんばかりに叫んでいるがゆきには聞こえない。
ゆきも叫ぶが、同じように広枝には聞こえない。
 言葉は聞こえないが、心が通じ合った姉妹の窓越しの会話は発車ギリギリまで続いた。
言葉は聞こえないが、心が通じ合った姉妹の窓越しの会話は発車ギリギリまで続いた。
その光景に住職までもが目を赤くしている。
発車のベルが鳴った。
ゆっくりと動きだした列車が、手を振るふたりを徐々に引き離していく。
小さくなっていく列車に手を振る広枝の胸に、ふと「もう2度とゆきには会えないのでは?」という不吉な思いがよぎった。
「ゆき…」
そんな思いを振り払うかのように、広枝は列車が見えなくなっても、なお手を振り続けた。
「広枝さん、帰ろうか」
広枝が福山駅を後にした頃、ゆきを乗せた列車は新尾道駅を発車していた。
「我が子を捨てた私は、福山に来てはいけなかったのでは?」
ゆきは、流れる風景を虚ろな目で見ながら、自分の胸に問いかけていた。
「明のためにも母として名乗り出るのはやめよう」
ゆきが、広枝から手渡された紙片を破り捨てた時、列車は三原駅に到着した。
第27話
「どうだった、福山は?姉さんに会えたかい?」
三原駅で降りたゆきを、ひとつ前の列車で到着していた監督がいつもの笑顔で迎えた。
誰が見ても明らかなゆきの腫れぼったい目について聞くこともなく、三原名物のタコの串刺しを目の前に差し出した。
「うわっ、美味しい!」 監督の優しさに味付けされた瀬戸内の味覚は格別でついさっきまで沈んでいたゆきの心をたちまち明るくさせた。
「さあ、出発するぞ!」
監督の気合の入った掛け声で『しまなみ物語』撮影隊一行は目的地の大三島に向けて出発した。
三原港から高速船に乗って生口島の瀬戸田で下船、多々羅大橋を渡れば大三島である。
佐木島、因島、そしてやや遠くに霞む向島。まるで箱庭細工のような風景は、さらにゆきの気持を和ませた。
終点の瀬戸田で降りた一行は、徒歩で多々羅大橋を渡った。

「大三島は『神の島』と呼ばれている神聖な島だ。旅館に入る前に、その神様が鎮座まします大山祇(おおやまづみ)神社に撮影終了までの無事を祈願するからな。それと境内には多くのクスノキが植えられているが、なかでも樹齢2600年といわれるクスノキには格別のパワーがあるらしいから、特に不浄の日々を送っている助監督と照明係は念を入れて願をかけるように…」
どこで仕入れたのか、監督の軽妙なウンチクに全員が声をあげて笑った。
さすがは推古天皇の時代から続く、全国に1万余の分社を持つ三島神社の総本社である。
今まで神の存在など熱心に信じたことがなかったゆきだったが、林立するクスノキの古木に囲まれていると、自然に神妙な気持ちにさせられる。
「どうか明が、明が、健やかな毎日を送れますように」――ゆきは祈った。
しかし、本心とは裏腹に「明に会いたい、会わせてください」とは祈らなかった。
合わせた手のひらの間にゆきの涙が落ちた。
第28話
「しまなみ物語」の撮影が始まった。
ゆきの役どころは、島の診療所の看護婦長である。
婦長といっても、医師は診療所長を含め2人、看護婦はわずか3人しかいない小さな診療所という設定である。
看護婦役は、大部屋女優時代に何度も演じたゆきにとっては勝手知ったる役であるはずなのだが、今回は初めての大役、それも主役である。
それだけにさっきから武者震いが止まらず、台本を読もうと思って広げても全然、目に入らない。
「いけない、いけない。落ち着かなくちゃ」
伸び上がって大きく深呼吸した時、控室のドアがノックされた。
撮影で何度も顔を会わせている助監督が、顔をのぞかせた。
「ゆきさん、出番です。お願いします。看護婦役はゆきさんの当たり役です。上がらず、いつもの調子で頑張ってくださいね」
「はい。よろしくお願いします」
 今までは、「は~い、集合、集合」と、その他大勢扱いされていたのが、控室も個室だし、周りの扱いも様変わり。うれしい反面、居心地の悪ささえ感じていたが、助監督の「ゆきさんの当たり役」という言葉にさっきまでの不安な思いが嘘のように消えていくのを感じた。
今までは、「は~い、集合、集合」と、その他大勢扱いされていたのが、控室も個室だし、周りの扱いも様変わり。うれしい反面、居心地の悪ささえ感じていたが、助監督の「ゆきさんの当たり役」という言葉にさっきまでの不安な思いが嘘のように消えていくのを感じた。
ゆきはもう一度、深呼吸して助監督の後に従った。
初日の撮影現場は、島の古い小学校を先乗りした大道具係が”改築”した診療所である。
「わあっ、本物の病院みたい」
診察室があるのは当然だが、2部屋とはいえ入院室もある。真新しい薬品棚もあるし、レントゲン室と書かれた木札が下がっている部屋さえある。
とても撮影用に作られた病院とは思えない出来栄えに驚いているゆきに監督から声がかかった。
「ゆきちゃんのナース姿はサマになってるねえ。今日撮るのは、東京から赴任してくるドクターを診療所の玄関で迎える場面だ。さあ、行くよ。カメラさん、OKね。ハイ、スタート」
カチンコが鳴った。
第29話
ゆきの相手役は昨年デビューした映画界期待のホープ・本郷裕一である。
映画の中のゆきの役名は山口洋子(ひろこ)、本郷は宮田彰良(あきら)。洋子は結婚間もなく夫を亡くした看護婦、裕一は個人病院を経営する父親が勧める結婚に反抗。家を飛び出して、この島の診療所に赴任してきた医師という設定である。
今日の撮影は、本郷が診療所に続く坂道を登ってくるシーンと、彼を迎えるゆきの初対面の場面である。
汗を拭きながら坂道を登る本郷にゆきが、背伸びをしながら声を張り上げる。
「宮田せんせ~い、彰良せんせ~い」
それに応えて本郷が笑顔で手を振る。
息はピッタリである。
「カ~ット!OK!さすがだねえ、ゆきちゃん。セリフもしっかりしてるし、初めての主役とは思えないほどの出来栄えだよ」
「すごいですねえ、ゆきさん。本当に主役は初めてなんですか。僕なんかより遥かに演技に芯が通っているし、グイグイ引っ張られるようで、圧倒されてしまいました」
本郷も目を丸くしながら称賛の声を上げた。
 「そんなにおだてても何も出ないわよ。きっとお参りした大山祇(おおやまづみ)神社のお陰よ」
「そんなにおだてても何も出ないわよ。きっとお参りした大山祇(おおやまづみ)神社のお陰よ」
そう言葉を返したもののゆき自身も、初の大役にもかかわらず、緊張もせず、自然な演技ができたことが不思議であった。
「さあ、この調子で次も行くよ~」
再び、監督の声がかかった。
「照明さん、しっかり頼むよ。レフ板をもっと上げて~」
「OKで~す!」
「用意、スタート!」
心地よい緊張感のなかでカチンコが鳴った。
「宮田彰良先生、ようこそ大三島診療所にお越し下さいました。看護婦長の山口洋子です。どうかよろしくお願いします」
ゆきが、島の畑で摘んだレンゲの花束を手渡した。
「新米医師の宮田彰良です。僕の方こそよろしく」
本郷が、額の汗もそのままに、はにかみながら花束を受け取った。
第30話
天気にも恵まれ、撮影は順調に進んだ。
夜中に急病患者が担ぎ込まれるというシーンでは、本当に午前零時を回ってから撮影が行われた。
温暖な気候の瀬戸内とはいえ、さすがに11月ともなると寒さが身に凍みる。
「本物は細部に宿る」と細かいところにも神経をとがらせる監督らしいこだわりはいつものことだが、大部屋時代に監督がメガホンを取った映画に何度も出演してきたゆきは準備万端。事前に用意したカイロをポケットに忍ばせていた 。
しかし、デビュー以来、今回で3作目の本郷にとって、夜中の撮影は初めてのこと。ゆきの横で白衣姿で寒さに震えていた。
「ゆきさんは寒くないのですか」
足踏みしながら、助けを求めるような顔で本郷が話しかけてきた。
「大丈夫よ。私には強い味方がありますから…」
ゆきは白衣のポケットからカイロを取り出して、本郷に手渡した。
 「あら、彰良さん、顔色が青いわよ。風邪を引いたんじゃないかしら」
「あら、彰良さん、顔色が青いわよ。風邪を引いたんじゃないかしら」
いつの間にやら、本郷に対する呼び方が本郷さんから「彰良さん」に変わっている。
本郷の額に手を当てた。
「大変!ひどい熱だわ。監督~、監督~。彰良先生が…」
ゆきは羽織っていたコートを本郷の背にかけて、抱きかかえるようにして控室へ運んだ。
「ドクターが本当に倒れたらシャレになんないよ」
軽口をたたきながら駆けつけてきた監督だったが、ゆきが本郷の額の汗を懸命にタオルで拭いているのを見て顔色が変わった。
「本郷くん、大丈夫か」
「監督、大事な場面で倒れてしまって申し訳ありません。少し休めば大丈夫です。それに私にはこれがありますから…」
本郷が大切な物を扱うように、懐からカイロを取り出して監督に見せた。
「ゆきさんから戴きました。お陰で身体が温まり随分、楽になりました」
「ふたりは年の離れた姉弟みたいだな。今夜は姉さんに看病してもらって早く治してくれよ、本郷君」
第31話
本郷の熱はなかなか下がらなかった。
ゆきは懸命に看病した。
化粧も落とさずナース服のままである。
小道具さんに借りた体温計で測ったら、なんと39度。何度もタオルを絞って本郷の額に乗せた。
しかし、顔中から吹き出る汗でタオルはすぐに生温かくなった。
さすがにゆきも不安になってきた。
「本郷さん、お医者様を呼びましょうか」
「大丈夫です。何しろあこがれのゆきさんに看病してもらってるんですから、ひと晩寝れば治りますよ。それより大事なシーンなのに迷惑をかけて申し訳ありません」
目を開けた本郷は気丈に答えるが、笑った顔は弱々しい。
たった一軒だが、島にも薬局はある。
が、明け方近い時刻に起こすわけにはいかない。
ゆきは途方に暮れた。
「どうしよう」――タオルを絞り過ぎて赤くなった手を本郷の額に置いた。
 本郷が目を閉じたままで口を開いた。
本郷が目を閉じたままで口を開いた。
「ゆきさんの手は、母さんの手みたいで心が落ち着きます」
「母さんの手みたいだなんて…」
本郷の言葉に、ゆきの心が波打った。
いくら明の幸せのためだったとはいえ、お腹を痛めた我が子を捨てた自分が、字こそ違うが、読み方が同じ「彰良先生」から「母さん」と呼ばれるとは…。
額に手を置いたままのゆきは、いつしか乳飲み子だった明の顔を思い出していた。
「明…」
小さくつぶやいた時、本郷の寝息が聞こえてきた。
我に返ったゆきは、そっと額から手を離した。
熱が少し下がったのか、本郷の顔からさっきまでの赤味が消えていた。
「もう大丈夫だわ。ぐっすりお眠りください。おやすみなさい」
夜が明けたのだろう。遠くでニワトリの鳴き声がしている。
「ああ、疲れた。私も少し休まなくちゃ」
伸びをして立ち上がったゆきの視界がぼやけた。
第32話
ゆきは夢を見ていた。
スポットライトが当たったステージで金ラメの入った白いジャケットを着た男がマイクを握っている。
声は聞こえないので、はっきりとは分からないが、多分、歌を歌っているのであろう。
「誰かしら?」
今まで会ったことのない顔である。
大部屋女優時代から、たとえ挨拶程度でも、一度でも会ったことがあれば絶対に忘れない特技を持つゆきだが、まったく思い浮かばない。
もどかしい気持ちで目を凝らすと、徐々にだが、顔の輪郭が見えてきた。
まだ若い。
20歳代であろうか。
前髪が汗が浮いた額にかかっている。
よく見ると切れ長の目がキラキラ光っている。
歌い終わったのか、客席に向かって深々と頭を下げている。
自然に、ゆきは拍手をしていた。
 「ゆきさん、どうしたんだ。大丈夫か?」
「ゆきさん、どうしたんだ。大丈夫か?」
頭の上で聞き覚えのある声がした。
「ん?」
ゆきは、ゆっくりと目を開けた。
顔の上に、心配そうに覗き込む監督の顔があった。
「あっ、監督。すみません。ついウトウトしてしまって…」
ゆきは、急いで起き上がり頭を下げた。
「いつもは現場に一番乗りのゆきちゃんが、部屋にいないので探していたんだよ。無事に見つかって良かったけど、気をつけてくれよ。本郷君に続いて、ゆきちゃんにも倒れられたら名監督もお手上げだからね」
「申し訳ありません。余計な心配をお掛けしてしまって…」
ふたりの会話に本郷が、目を覚ました。
「あっ、監督。それにゆきさんも…」
状況が呑み込めていないのか、本郷はあたりをキョロキョロ見回している。
「本郷君。ゆきちゃんは、ひと晩中、寝ずの看病を続けてくれたんだぞ」
「エッ、ずっとですか!ありがとうございました」
本郷は目を潤ませながらゆきの顔を見つめた。
第33話
「ご迷惑をお掛けしました。もう大丈夫ですから」
撮影の遅れを気にした本郷が撮影の再開を監督に直訴した。
「ゆきちゃんも寝てないだろうから、今日は大事をとって休みにしよう。ドクターとナースが病人みたいな顔をしていたら締まらないからね(笑)。明日は観客の涙を頂く、この作品のクライマックスをバチンと撮るんだから、ふたりともしっかり休養をとって明日の撮影に備えてくれよ」
監督が出て行った部屋に静けさが戻った。
ふたりの胸の鼓動が聞こえるような静寂である。
ゆきは、本郷とこのままずっと居たいと思う気持を振り切って口を開いた。
「じゃ、わたしも自分の部屋に戻りますから…」
腰を上げかけたゆきの手を本郷が握った。
「ゆきさん、本当にありがとう」
柔らかく、温かい手だった。
その手で肩を抱かれた。
ぐっと引き寄せられた。
本郷の顔がすぐ目の前に迫ってきた。
ゆきは金縛りにあったように体が動かなくなった。
 「ゆきさん…」
「ゆきさん…」
ゆきは瞼を閉じた。
本郷の唇が重ねられた。
「ああ…」
思わず吐息を洩らした。
ゆきは崩れ落ちそうになった。
あわてた本郷が唇を離した。
「すみません。つい…。ごめんなさい」
一歩下がった本郷が、バツの悪そうな顔でゆきに謝った。
「婦長、明日からの撮影もよろしくお願いします」
照れ隠しなのだろう、宮田彰良の顔に戻った本郷が明るい声で頭を下げた。
「明日は大切なシーンの撮影だからお互いに頑張りましょう、彰良先生」
ゆきも何事もなかったかのように返して本郷の部屋を出た。
自分の部屋に戻る途中、ゆきはまた監督に会った。
どきりとした。
「昨夜は寝てないんだから少し、休んでおけよ」
「はい」
顔が火照ってくるのを感じながら、ゆきは小さな声で答えた。
第34話
翌日は早朝から撮影が再開された。
本郷もゆきも昨日とは打って変わった輝いた表情である。
「今日は彰良が洋子に許されない愛を告白する場面だ。ここは観客を泣かせる最大の山場だからね。リハ通りバッチリ頼むよ。カメラさん、照明さん、スタンバイOKかな。用意、スタート」
 カチンコが鳴った。
カチンコが鳴った。
見つめ合う洋子と彰良をカメラがアップで追う。
洋子の目から涙がどっとあふれる。
その涙を彰良が涙を唇で受け止める。
なおも泣きじゃくる洋子を彰良が抱きしめる。
「ハ~イ、カット。いいよ、いいよ。OK、OK!どうしたんだい、ふたりとも。リハより何倍もいいじゃないか。自然な演技で俺まで泣けてきちゃったよ。次回作もゆきちゃんと本郷君のコンビで決まりだな」
ゆき自身もスムーズな演技ができたことが不思議であった。
「ひょっとすると昨日の本郷とのことは、『演技の神様』がくれたプレゼントだったのかしら」
心の中で独り悦に入ってていたゆきに、クライマックス場面の撮影を1回で撮り終えたことがうれしかったのであろう、上機嫌の監督から声が掛かった。
「さあ、次もこの調子で行くよ」
その後の撮影も『神様』のお陰で?トントン拍子で進み、予定より1週間も早く撮影は終了した。
撮影スタッフ全員を前に監督が声を張り上げた。
いつもは青白い監督の顔が紅潮している。
「みんな、ご苦労さん。無事に撮影を終えることができた。ありがとう。今日はこれから無事撮影が終了したことの御礼とヒット祈願を兼ねて大三島神社にお参りに行くぞ」
直ちにスタッフ全員がバスで神社に向かった。
監督の横にゆきと本郷が並んで座った。
「封切は来月末だ。当日は東京、大阪、それと広島で舞台挨拶があるからな」
「広島…」
ゆきの脳裡に夢で見た白いジャケットを着た若者の顔が浮かんだ。
第35話
年が明け、封切の日まで1週間を切った。
ゆきは、撮影終了直後から新たなポスターの撮影や宣伝のための雑誌や新聞、テレビの取材などに追われた。
大部屋女優時代には想像もしなかった激務に体重は10キロ近く減った。
封切初日の劇場挨拶の打ち合わせで、久しぶりに顔を会わせた監督が、げっそりと痩せたゆきを見て心配そうに声をかけた。
「顔色が悪いぞ。どこか悪いんじゃないか。病院へ行ったのか。これが当たれば、次回作もゆきちゃん主演で撮ろうと企画を練っているんだから大事にしてくれよ」
「大丈夫です。ずっと強行軍だったので、少しばかり疲れているだけです。ご心配をおかけして申し訳ありません」
 自分でも、どこかおかしいのではと感じていたが、ゆきは気丈に答えた。
自分でも、どこかおかしいのではと感じていたが、ゆきは気丈に答えた。
ちょうどそこへ、別の作品の撮影を終えた本郷裕一が到着した。
本郷も、少し顔を会わせない間のゆきの激やせぶりに驚いたが、口には出さず「洋子婦長、具合が悪くなったら、すぐに宮田先生に診てもらうのですよ」と、おどけた表情で言った。
「彰良先生にそこまで心配してもらったからには早く元気にならなくちゃね」
本郷の軽口に調子を合わせて笑顔で答えたゆきだったが、心の中ではもどかしさに包まれた不安が次第に大きくなっているのを感じていた。
全員が揃ったところで、劇場挨拶当日のスケジュールについて監督が説明を始めた。
「少々きついかもしれんが、各映画館の上映時間の都合で東京、大阪、広島と1日で回るからな。挨拶は各館30分。広島は夜の部になるが、ゆきちゃんは、せっかくの機会だから福山の姉さんを招待してあげたらどうだ」
撮影現場では厳しいが、それとなく気遣ってくれる監督の優しさに、ゆきは嬉しくなった。
「はい。姉もきっと喜ぶと思い…」
最後まで言い終わらないうちに、ふっと目の前が闇に包まれた。
第36話
「ゆきちゃん、ゆきちゃん。しっかりしろ」
監督の声でゆきは、目を開けた。
「大丈夫か?劇場挨拶は取りやめにした方がいいんじゃないか」
「ちょっとめまいがしただけです。ただの寝不足ですから、今晩ぐっすり眠れば大丈夫です。監督、お願いですから封切の挨拶には連れて行って下さい」
ゆきの懇願に、出発の前日までの静養を条件に監督も折れた。
ゆきは、監督の言いつけ通り、その日から部屋から一歩も出ず、劇場挨拶当日の朝まで眠り続けた。
1回目の有楽町の劇場での挨拶は午前11時からだが、まだ夜も明けぬ5時に目をさました。
外は真っ暗だが、十分な睡眠を摂ったことで気分は爽快だった。

「やっぱり寝不足のせいだったんだわ」
シャワーを浴びた後、いつものようにラジオのスイッチを入れた。
歌謡番組のようである。
三面鏡の前で濡れた髪にブラシをかけながらラジオに耳を傾けた。
「さて、次の曲は現在有線放送で大人気の『伊香保挽歌』です。この曲は、広島県福山市出身の歌手・橘あきらさんのデビュー曲で橘さん自身が作詞・作曲したものです」
司会者の紹介が終わり、イントロに続いて哀愁を帯びた声が流れて来た。
瞼閉じれば 哀愁の町 尽きぬ心を 残して生きた 今日は湯の香に漂う一人の旅路~~
「橘」は芸名だろうが、名前が「あきら」、出身地が「福山市」、そして歌の舞台が生まれ故郷の「伊香保」――ゆきにとって忘れられない名前であり、地名ばかりである。
「まさか?」、「ひょっとして?」と思いをめぐらせながら、ゆきは手を止めて歌に聞き入った。
「でも偶然かも?いや、きっと偶然だわ」
ゆきは、釈然としない気持ちを抱きながらも、化粧を始めた。
ラジオからは次の曲が流れ始めたが、いつしかゆきは、さっき聞いたばかりの『伊香保挽歌』の歌詞を口ずさんでいた。
第37話
東京・有楽町劇場での封切初日の挨拶は定刻の11時に始まった。
舞台の袖で待つゆきにとって、大部屋女優時代には想像もできなかった夢舞だけに、うれしさと緊張で胸が一杯であった。
司会者の案内で監督を先頭に主だった出演者が順にステージに上がった。
ゆきをはさんで中央に監督と本郷が立った。
司会者が出演者ひとりひとりを紹介した。
まばゆいライトに照らされた白衣姿のゆきに観客は割れんばかりの拍手を送った。
ゆきの横に立つ本郷も、今日ばかりは、引き立て役である。
最前列に座るカメラマン席から間断なくフラッシュ が光る。
「ゆきちゃんと本郷君の熱演で、監督人生で最高傑作とも言える映画を撮ることができました。一世一代絶対の自信作です」
司会者から最初にマイクを渡された監督が、いつになく上気した顔で答えた。
 続いて、ゆきにマイクが回ってきた。
続いて、ゆきにマイクが回ってきた。
さっきまでの足の震えはいつしか止まっていた。
「身に余る大役だったのですが、監督はじめ、スタッフの皆様や本郷さんたちのお蔭で、それに撮影をした大三島の大山祇神様(おおやまねずのかみさま)に背中を押してもらって素晴らしい作品になったと思います。是非、劇場に足をお運びください」
ゆきの絶妙なコメントに会場から、また大きな拍手が起こった。
その後、参加者全員で集合写真を撮影、劇場挨拶を終えた一行は、すぐさま新幹線で大阪に向かった。
「満員の会場であんな素敵な挨拶ができるんですから、さすがですね。神様もゆきさんに感謝されたら、応援しないわけにはいかないでしょうね」
隣の席から本郷がしきりに話しかけてくる。
いつものゆきなら笑顔で答えを返すのだが、今日は口を開くのも億劫だった。
疲れだけではない。頭の芯が痺れているのである。
何度も奈落の底に沈むような悪寒を覚えながら、いつしかゆきは、深い眠りに落ちていた。
第38話
超満員の大阪・新梅田劇場での封切挨拶も大盛況のうちに終った。
舞台に上がっていた時は気が張っていたせいか、それほど感じなかったが、終わった直後から、今までとは違う激しい痛みが頭全体に広がってきた。
しかし、次は楽しみにしていた広島。そんなことは言っていられない。
額に薄っすらと汗をにじませたゆきに監督が、「無理だったら休んでもいいんだぞ」と声をかけたが、ゆきは「福山の姉さんも観に来てくれるはずですし、最後まで頑張ります」と、額にハンカチを当てながら答えた。
「のぞみ」が滑り込むように広島駅に到着した。
14番線ホームに姉夫婦と住職の姿があった。
「まあ、住職さんまで。ご無沙汰しています。お忙しいところをありがとうございます」
「大事ない、大事ない。ゆきさんの晴れ姿をひと目見たいと思うてな」
監督に姉夫婦と住職を紹介した。
 型通りの挨拶を終えた監督が、ゆきを手招きして耳元でささやいた。
型通りの挨拶を終えた監督が、ゆきを手招きして耳元でささやいた。
「流川シネマ館は広島駅から近いし、歩いても10分ほどだ。せっかく姉さんが来てくれたんだし、俺たちは先に行ってるから、ゆきちゃんは姉さんたちと一緒に来ればいいよ。今夜は広島泊りだし、終わったら本郷君たちも呼んで食事でもしようじゃないか」
「わぁい。じゃあ、お言葉に甘えて…」
ゆきが、本郷らが待つ改札口に急ぐ監督の後ろ姿に頭を下げようとした瞬間、目の前に霞がかかり、足がもつれそうになった。
咄嗟に、広枝がゆきを支えた。
「ゆき、危ない。気ィつけにゃあいけんよ」
「今日は朝が早かったし東京から広島まで1日中、新幹線で移動だったから」
「身体が一番の財産なんじゃけえ労わらにゃあ」
「はい、広枝お姉さま」
内心の不安を悟られまいと、ゆきは幼い頃の口癖で広枝の言葉を遮った。
「広枝お姉さまだなんて何年ぶりかしら。ところで明のことだけど…」
「えっ、明…」
第39話
次の言葉が出ぬまま、ゆきは広枝の腕の中に倒れこんだ。
「ゆき、ゆき。どうしたの、ゆき」
半狂乱の広枝が、懸命に話しかけた。血の気が消えたゆきの顔は、まるで蝋人形のようである。
「早く、救急車を…」
住職が大声で叫んだ時、ゆきが、うっすらと目を開けた。
「ゆき、大丈夫?」
広枝の問いかけに、ゆきは、無理に作った笑顔でうなずいた。
「もう平気。ちょっと眩暈がしただけだから…」
ゆきの頬に赤味が徐々に戻って来た。
 「無理をしないで流川シネマ館での挨拶はお休みさせて戴いたら…」
「無理をしないで流川シネマ館での挨拶はお休みさせて戴いたら…」
不安顔の広枝の言葉を、ゆきは、すがるような表情で遮った。
「いえ。私のために監督が、わざわざ広島での挨拶を会社に申し出てくれたんだから絶対に舞台に立ちます」
ゆきの強い決意にさすがの広枝も折れた。
住職に肩を借りてゆきは改札口に急いだ。
流川シネマ館に向かうタクシーの中で、ゆきは広枝に小声で聞いた。
「お姉さま、さっき明のことを言ってたけど、明がどうかしたの?」
「うん。明は私たちにも内緒で歌手になったのよ。名前は橘あきら…」
「えっ、明が歌手に?」
思いがけない広枝の話にゆきは驚愕した。
「今、明自身が作詞・作曲した『伊香保挽歌』のキャンペーンで下関に来てるんだけど、それが終わり次第、広島に寄ることになっとるんよ」
「橘あきら」、「伊香保挽歌」――今朝、偶然にラジオで聞いた曲は、明の歌。そして今夜、その明に…。
生まれて間もなく、姉に託して以来、片時も忘れたことがなかった我が子に20年ぶりに、しかも、ゆきにとってこのうえない晴れの舞台の日に会える…。
ゆきは、人生の奇遇さに思わず目頭を押さえた。
流川シネマ館前で監督一行と合流したゆきは、胸の動悸を押さえながらスクリーン裏の控室に入った。
第40話(最終話)
監督の先導で舞台に上がったゆきにひときわ大きな拍手が送られた。
館内の熱気は最高潮。客席からの声援に笑顔のゆきが手を振る。
ちょうど、そこへ明が、劇場に到着した。
前へ行きたくても超満員で身動きがとれない。
仕方なく立ち見である。
遠くに『しまなみ物語』の主演女優のまばゆいばかりの美しい顔が見える。
本郷に手を引かれたゆきが、マイクの前に立った。
と、その時、突然ゆきが腰から崩れ落ちた。
監督と本郷が駆け寄る。
舞台の袖で見守っていた広枝が悲鳴を上げる。
客席も総立ちになった。
「早く、救急車を呼べ」
誰かが叫んだ。
幕が降ろされた舞台から本郷に抱きかかえられたゆきが、控室に運ばれた。
「ゆきさん、ゆきさん」
本郷が懸命に呼びかけるが、反応はない。
ストレッチャーを押した救急隊員が到着した。
ゆきの顔色を一見した隊員は、すぐさま救急車に運び込んで病院に向かった。
救急車には広枝が付き添っていた。
「せっかく明と…」
笑みを浮かべたような表情で目を閉じたゆきの頬をそっと撫でた。
 ゆきは、夢を見ていた。
ゆきは、夢を見ていた。
明に手を引かれて故郷の伊香保温泉の石段を上っていた。
夢の中の明は、いつか見た白いブレザー姿である。
「母ちゃん」、「明」
母ちゃんと呼ばれた嬉しさに、ゆきの胸が震えた。
石段をひとつ上る度に、ふたりは見つめ合った。
明の切れ長の目は、ゆきに瓜ふたつである。
「母ちゃん、俺が作詞・作曲した『伊香保挽歌』を一緒に歌おうか」
「明が作った歌だもの、歌うわよ。でも初めてだから上手く歌えるかな」
まぶた閉じれば哀愁の町 尽きぬ思いを心残して生きた 今日は湯の香漂う一人の旅路 来ました湯の町 夢の中まで 思い出すのは霧の階段 伊香保の町
歌い終わったふたりは、また顔を見合わせた。
いつの間にか母と子を深い霧が包んでいた。(了)
